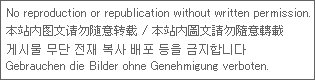
「ナナはいつもキズだらけ」小説(本編番外編)
くもちゃん、と呼ばれた気がした。
まだフワフワとした意識のなか、魔法のような自覚が俺を現実に引き戻す。
くわしい内容は忘れてしまった、けれどなにかとてもいい夢を見ていた気がする。隣には当たり前のようにあの子がいて、幸せそうに微笑んでいて、俺は夢のなかでも、その事実だけで胸がいっぱいになる。
薄く目を開くと、いつの間に目覚めていたのか、一緒に眠りに落ちたはずのナナがすっかりと朝の顔で、大きな瞳をぱちぱちさせながら、距離わずか10センチほどのところから俺の顔をじっと見つめていた。一組の布団のなかにぴっとりと寄り添い、身体を向き合わせて眠るいつもの体勢は昨晩眠る前からほとんど変わっていない。ナナも俺も、寝相は抜群にいいのだ。
「…ナナ」
寝起きで掠れた声は思った以上にしっかりとその名を唱えた。その瞬間、ナナは花が開くように笑み、またひとつくもちゃん、と呼ぶ。もちろん――――本当はそんなふうに言い切りたくなんてないけれど――――ナナの心から聴こえてくる、声にはならない声で。
ナナの腰あたりにまわしたままだった右腕を、ナナの身体の線を辿るようにしてスルスルと持ち上げると、そのまま右の手の先でナナの頬を撫ぜる。ナナは目を細めて、俺の手に自分の頬を擦り寄せる。
「おはよう、ナナ」
言ってから、ナナの後頭部へゆっくりと手のひらを動かす。まっ黒な猫っ毛さえ、ナナの想いを懸命に伝えようとしているみたいに揺れて、くすぐったい気持ちになる。俺は少しだけ上半身を浮き上げると、ナナの唇にキスを落とした。
それは、おはようのキス。すぐに顔を離すと、ナナからもおはようの笑みが返ってくる。
目が覚めるような碧色の瞳の輝きは純真そのもので、だけどそれでいて官能的な甘さを含んでいる。それが飾らないナナのそのままのまなざしなのだから余計に悩ましい。俺は胸のざわめきを押し込め、二つ目のキスをする。今度は、大好きだよ、のキス。
小さなリップ音がいくつか連なって初冬の冷たい空気にていねいに震える。キスの最中、ほっそりと骨ばった手がツツ…と俺の首すじを伝ってきて、首の真ん中あたりで弱々しく止まる。ナナの手はひんやりと冷たくて、心細い。
交互に唇を啄みあいながら、俺はその手を指先から絡め取り、深く手を繋ぐ。ナナの口のわずかな隙間からはあっと音のない息がこぼれて、俺はその瞬間、たまらなくナナのすべてに触れたくなる。
おそろしくなるほどに、この子が愛しい。
土曜日の午前7時。
ナナのおじいさんとおばあさんは早々に起きて活動を始めていて、一軒家の一階のナナの部屋には、リビングの静かな生活の音が響いてくる。いま、キッチンでコンロの火がひとつついた。あと20分もすれば、この部屋にも朝ご飯に呼ぶ声がかかるだろう。
カーテンを開けるために立ち上がる数秒さえ惜しくて、ほのかに差し込む陽の光だけを頼りに、俺とナナは「会話」をする。布団に並んで横になったまま身体をぐるりと下向きにすると、ナナは枕もとに置いていたノートを広げる。
《くもちゃん だいすき》
さらさら、と、ノートを滑らせた今日最初のナナの言葉。
「俺も、ナナが大好きだよ」
俺が応えると、ナナはふにゃっと嬉しそうに笑う。わーい、と言っているみたいだ。
《きょうはね くもちゃんのゆめをみたの》
「ほんと? …今日は、どうだった?」
《ナナは くもちゃんがみえるけど くもちゃんはナナがみえなくて ナナかなしかった》
「……そっか」
《くもちゃんってよびたくて でも ナナこえがでないから よべなくて くもちゃん とおくにあるいていっちゃった》
「………」
《だから くもちゃんがおきて ナナのことみえて しあわせ》
「…うん」
俺は、無邪気に微笑むナナの頭をそっと撫でた。
ナナは毎日のようによくない夢ばかり見るようで、それがナナの心のバランスが崩れているタイミングと重なると、悪い相乗効果を起こして過呼吸や自傷を引き起こしてしまう。
それでもいまはずいぶん落ち着いたほうで、こんなふうに一緒に眠れる日はとくに安定していて、自傷もほとんどせず過ごせている。けれどナナの不調には予兆というものがないので、元気に見えた日に突然不安定になり、俺の見えないところで泣いていたり、腕を切っていることがままある。
ナナのパジャマの裾からのぞく左腕の手首には、無数の切り痕が痛々しく刻まれ、それらはいまなお増え続けている。か細いこの腕にこれまでどれほどの痛みがはしったのか、ナナがどれほどの苦しみや悲しみに耐え抜いてきたのか、想像しようとしただけでも、俺は息ができなくなりそうになる。
「…俺の夢にも、ナナがきてくれたよ。どんな夢だったかは、よく覚えてないんだけど…ナナがすごくしあわせそうに笑ってて、俺もすごく嬉しかったのは覚えてる。俺の夢のなかに、ナナを呼んであげられたらいいのにな」
「……」
ナナが、にこっと笑む。
《くもちゃんのゆめにもナナがいて ナナのゆめにもナナがいて ふしぎだね》
「うん」
幼なさを残すナナの言動は、可愛くて、少しせつない。
「ナナ、今日は、何がしたい?」
ナナは少し思考に走るものの、わりと悩むことなくすらすらと書きだす。
《くもちゃんのおうち いきたいな》
「うち、でいいの? 母さん、ナナが来てくれたら喜ぶよ」
ナナは、えへへ、とくすぐったそうに笑んだ。ナナは俺の家をとても好きみたいだ。
母親が趣味のガーデニングで植えている花々、プロレベルと近所でも名高い手づくりのお菓子、父親お手製の陶芸品、ふらっと里帰りするハイテンションな10歳上の姉のマシンガントーク。俺と一つ違いで、県内トップの私立校に主席入学を果たした優秀な兄。兄とはよく「似てる」と言われ、ナナも、思いがけず嫉妬してしまうほどに兄に懐いている。
俺は、ナナに出逢うまで、自分の家が特別だなんて思ったこともなかった。
事実、母親は専業主婦で、父親はふつうのサラリーマンで、どこにでも存在するような、ごくありふれた一般家庭だ。
でも、そんなありふれた一般家庭は、ナナにとってはまるで異国かテーマパークのような場所だった。
「…そういえばこないだ、キスしてるの、父さんに見られちゃったね」
思い出して、恥ずかしくなりながら言うと、ナナがいたずらっ子のように肩をすぼめる。
「とくに何にも言われないけど、なんか、しばらく父さんのほうが恥ずかしそうにしてたよ」
ナナがボールペンを滑らせる。
《こんどは こっそり だね》
ナナが左手の人差し指を口元に当てて「ないしょ」の仕草をした。
俺は堪らずぎゅっとナナを抱きしめて、そうだね、と囁いた。
「洋平くん、ナナ、朝ご飯よ〜」
戸の向こうから、おばあさんの元気な声が飛んできた。返事ができないナナの代わりに、いま行きます、となるべく大きく声を返す。
「行こ、ナナ」
うん。ナナがこくりとうなづいて、それから一緒に立ち上がって、戸の前まで手をつないで歩く。戸の先で、温かいお味噌汁のにおいがする。
いつもの、ありふれた朝。
幸福と少しの切なさと、不安や悲しみやこぼれそうな愛しさのなかで訪れる、長い日常の一日。
当たり前の顔をしてやってくる、ナナのいてくれる一日を、今日も大切にしたいと心に強く思う。
当たり前で、特別な朝。時刻は現在7時20分。
fin...
2014.10.05 UP
「当たり前で、特別な朝」
